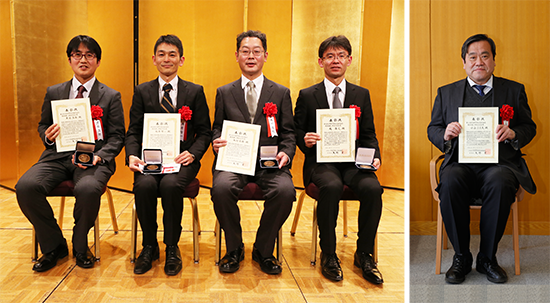�N�䌒��Y���L�O�ܗ����
��37��i2021�N�x�j

�u��37��N�䌒��Y���L�O��ҁv
�i������j�@���� �T�厁�A�Ö� ��T���A�� �F�����A�R�� �����@�@
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
�Ö@��T
�@�F��
�����@�T��
�R��@�� |
�\�j�[�������
���f�B�J���r�W�l�X�O���[�v
���f�B�J���v����
���i�v�Q��
��������
�v���W�F�N�g�}�l�[�W��
�V�j�A�I�v�e�B�J���G���W�j�A
�V�j�A�n�[�h�E�F�A�G���W�j�A
|
�u�X�y�N�g����͌^�t���[�T�C�g���[�^�[�J���Ǝ��p���v
�@��҂�̓u���[���C�f�B�X�N���u�Ŕ|���������ړ������̂̌����o�Z�p�����ƂɁA����J�������Ɨ�����^32ch���d�q���{�ǂƏd�ݕt�ŏ����@�A���S���Y����g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A���E���̃X�y�N�g����͌^�t���[�T�C�g���[�^�[���������A���i�������B���̑��u�ł̓X�y�N�g�� �A���~�L�V���O������p���邱�ƂŌ��o�u���������I�ɑ��������A�܂��]���@�̌��_�ł������u�����x��Č��������������B���̌��ʁA���E�ō����\��7���[�U�[��N�ɂ��44�F�ȏ�̌u�����o�̎����ɐ��������B���̑��u�͋ɂ߂ĕ���\���������ߍ����O�̐�[��Ì����@�ւŗ��p����A����Ɖu�E�����nj����ɑ傫���v�����Ă���B���ł̐V���Ȍ����u�̎����͎Љ�I�v�����傫���B
�@���Ђ̌��f�B�X�N���u�̋Z�p��S���V��������ɓW�J�������\�Ȍ����u�������������Ƃ́A���̑����m�̏d�v�������������̂ŁA����̉䂪���̌��Y�Ƃ̖͔͂ƂȂ�D�ꂽ�Ɛтł���B
|
��36��i2020�N�x�j

�u��36��N�䌒��Y���L�O��ҁv
�i�����j���� �����A���R �����A�R �G�T��
�i�O����j�@�@�@�哇 �����A�@�{�� �͎��@�@�@�@�@�@
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
|
�{��@�� |
�ˈ����l��w�@��p�H�w��
�Տ��H�w�ȁ@���C����
������w�@��[�Ȋw�Z�p�����Z���^�[�E�t�F���[ |
�u�L�@���@�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̐��I�����v
�@��҂́A2009�N�ɏL��������у��E�����n�y���u�X�J�C�g�������D�ꂽ���d�w�Ƃ��ċ@�\���邱�Ƃ����o���A�L�@���@�y���u�X�J�C�g���z�d�r�𐢊E�ɐ�삯�ĊJ�������B����ɁA���̐��ʂɗ��r���ĒP�����V���R�����z�d�r�ɔ���ϊ�������B������ƂƂ��ɁA�y���u�X�J�C�g���z�d�r�̌����J�����������A���̕���̌����J�����L���邱�Ƃɍv�������B�y���u�X�J�C�g�ޗ��́A�쐻�@����r�I�ȕւł���A�����E��ʐ��Y�̉\����L����ƂƂ��ɁA�ޗ��̈��萫����Ȃ�тɉ���p���Ȃ��ޗ��n�̊J�����L���i�W���Ă��邽�߁A����A�����\�Љ���\�z���邽�߂̑��z�d�r�ޗ��̂P�Ƃ��Ĕ��W���傢�Ɋ��҂����B ��L�̐V���z�d�r�ޗ��̐��I�J���Ȃ�тɂ��̕���̌����҂Ƃ��Ă̐��ʂ́A���Y�ƋZ�p�̍���̔��W�ɍv������Ƃ��낪�傫���D�ꂽ�Ɛтł���B |
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
| �哇�@�� | ������� �L�c����������
�ޗ��E�v���Z�X�P���@�������[�_�[
�@
|
�u�����̃��[�U���H�ɂ��G���W���p�����ϑw���`�o���u�V�[�g�̎����v
�@��҂�́A�����ԗp�G���W���o���u�𒅍������郊���O��̕��i�ł���o���u�V�[�g�̐����ɁA���o�͔����̃��[�U�ɂ������ϑw���`�Z�p�𐢊E�ŏ��߂ēK�p���邱�Ƃɂ��A�ϖ��Ր���ϔM���͂��Ƃ��A�z�C�|�[�g�̐v���R�x�������サ�A�����݂̂Ȃ炸�L���C�O���Y�����\�ɂ��A�{�i�I�Ȏ��p���ɍv�������B�{�Z�p�̊J���ɂ́A���[�U�N���b�h�o���u�V�[�g�̌��^���J�����������ɗp���Ă���CO2���[�U���̃��[�U�ɒu�������邱�Ƃɂ����H�V�X�e�������^�E���������������ƁA�y�т��̉��H�V�X�e���ɍœK�ȃN���b�h�p�����������J���ł������ƂȂǂ��傫����^���Ă���B �����`�@�͂R�������H�̗L�͂Ȏ�i�Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă��邪�A���̐��������{���̂悤�Ɋ�Y�Ƃ̐S�����Ō������g�p���̉��A���t�B�[���h�ʼnғ����Ă��邱�Ƃ́A����߂ĈӋ`�[�����Ƃł���A�킪���̌��Y�Ƃ̔��W�ɑ傫���v������D�ꂽ�Ɛтł���B |
| �����@�� | ������� �L�c����������
�ޗ��E�v���Z�X�P���@��������
�@
|
| ���R �Ď� | �g���^�����Ԋ������
���m����Z�p�J����
��擝���� �劲
�@
|
| �R �G�T | �g���^�����Ԋ������
���m����Z�p�J����
��[�R�A�Z�p�J���� ��C
�@
|
��35��i2019�N�x�j

�u��35��N�䌒��Y���L�O��ҁv
�i������j ���c �_�i���A ��� �F�����A ���� �T�����A ���� ��A��
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
| ���� �T�� | ���{�d�M�d�b�������
��[�W�σf�o�C�X������
��ȓ��ʌ�����
�@
|
�u�Ⴕ�����l�E���������̃����u�������[�U�̊J���v
�@��҂�́A���ڕϒ����[�U�̌����ɂ����ă����u�����\����K�p���邱�Ƃɂ��t�H�g�j�b�N�������[�U�ł͐��E�ŏ��̂������l�ƒ����d�͓����B�������B�܂��A�َ�ޗ���̒��ڐڍ��Z�p��p���Ėʔ������[�U�Ɠ����̒����d��Si ��チ���u�������[�U�����������B����ɁASiC���Ƀ����u�������[�U���쐻���A���t�B�[�h�o�b�N���ʂ�p���邱�Ƃɂ��A���ڕϒ��ł͐��E�ő���256Gb/s-PAM4�ɐ��������B�����̐��ʂ́A�f�[�^�Z���^���C���^�[�R�l�N�g�̑�e�ʉ��ɉ����A�����̃{�[�h���ACPU�����C���^�[�R�l�N�g���\�ɂ��钼�ڕϒ����[�U�̐V���ȉ\�������B
�@����A�f�[�^�Z���^���ł̑�e�ʒ��������ʐM�����̎��v���܂��܂����܂����ŁA�}���ȋC��ϓ���}�~���A�n��������邽�߂ɂ��A�ȃG�l���M�[���ʂ��K�v�Ƃ���Ă���B�{�������ʂ́A���̗��҂̗v���ɓK��������̂ł���A���Y�Ƃ̔��W�ɑ傫���v������D�ꂽ�Ɛтł���B |
| ��� �F�� | ���{�d�M�d�b�������
��[�W�σf�o�C�X������
��C������
2019�N4���` ����c��w �y����
�@
|
| ���� ��A | ���{�d�M�d�b�������
��[�W�σf�o�C�X������
��C������
�@ |
| ���c �_�i | ���{�d�M�d�b�������
��[�W�σf�o�C�X������
��C������
�@ |
��34��i2018�N�x�A����30�N�x�j

�u��34��N�䌒��Y���L�O��ҁv
�i������j���� ���i���A�R�{ �C�����A���c �a�㎁�A�H�� ���厁
�i�O����j���V ���s���A���� �Ðm���A�R�� �������A�}�� ���F��
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
|
�R�� ���� | �l���z�g�j�N�X�������
���������� ���T�[�`�t�F���[
|
�u�����\�ʎq�J�X�P�[�h���[�U�̌����J������ю��p���v
�@��҂�́A���ԊO�̈�̗ʎq�J�X�P�[�h���[�U�̊J���Ɏ��g�݁A�d�q�g�����̐����Ȍv�Z�Ɋ�Â��Ԑڒ�����N�⌋����d��ʏ��ʍ\��(DAU)�̔��Ăɂ��A�ɂ߂č������x���萫�Ɣ����g���̍L�ш扻���������A���i�������B�܂��A�P��f�o�C�X���ł̒��ԊO2�g�����U���[�U�̋��U��������g�����ɂ��A��������e���w���c��������������ȂǁA�X�Ȃ�g����̊J��ɂ����g��ł���B
�@���̗ʎq�J�X�P�[�h���[�U�̊J���E���p���́A�K�X�Z���V���O��C�t�T�C�G���X����ɂ�����v���ւ̕��L�����p�ƂƂ��ɁA�Ő�[�̌��Ȋw�������x����d�v�Ȍ��f�o�C�X�ł���A����̌��Y�Ƃ̔��W�ɍv������D�ꂽ�Ɛтł���B
|
| �}�� ���F | �l���z�g�j�N�X�������
���������� �ޗ�������
����������
|
| ���c �a�� | �l���z�g�j�N�X�������
���������� �ޗ�������
|
| �H�� ���� | �l���z�g�j�N�X�������
���[�U���Ɛ��i��
��������53����
��C����
|
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
|
���� �Ðm | �O�H�d�@�������
�����́E�f�o�C�X���Ɩ{��
�Z�t�� |
�u���^���o�͕��ʓ��g�H�^���[�U�[�̊J���ƕ��v�����C�_�[�ւ̉��p�v
�@��҂�́A�ő̃��[�U�[�ޗ����R�A�ɍ̗p�������ʓ��g�H�\���ɂ�苭���������߂�}��ƂƂ��ɁA���[�U�[�������̕��ʓ��g�H���ő����˂����đ�������Ǝ��̏��^�������E���[�U�[�\���̊J���ɂ��A���o�͉��������Er,Yb:�K���X�ޗ��ł̒P�ꃂ�[�h���o�͂Ƃ��ĕ���24W�A �s�[�N��20KW�Ƃ������E�ō��o�͂����������B����1.5��m�A�C�Z�[�t�g���тł̍��i���E���o�͂̃��[�U�[�E������́A���v�����C�_�[�ɓK�p����A���E�ō��̊ϑ����\�������A�H�c��`���͂��߁A�����O�̎�v��`�֔z������Ă���B
�@�����V�\���E�����\�̃��[�U�[�E������̊J���ƕ��v�����C�_�[�ւ̉��p�́A�q��@�^�q�̈��S����Ɏ�����ƂƂ��ɁA�ő̃��[�U�[�̗��p������g�債�A���Y�Ƃ̔��W�ɑ傫���v������D�ꂽ�Ɛтł���B
|
| ���V ���s | �O�H�d�@�������
���Z�p����������
���Z�p�� ��ȋZ�t��
|
| �R�{ �C�� | �O�H�d�@�������
�����g���f�o�C�X���쏊
���f�o�C�X�� �f�o�C�X
���� ��C
|
| ���� ���i | �O�H�d�@�������
�ʐM�@���쏊
�d�q�f�o�C�X������ꕔ
�d�q�NjZ�p�� ��C
|
��33��i2017�N�x�A����29�N�x�j

�u��33��N�䌒��Y���L�O��ҁv
�i������j�� ���� ���A ���{ �y�� ���A�`�� �O�i ��
�i�O����j���� �h�O ���A ���� �[ ���A�a�� �v ���A�n�� �r���Y ��
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
|
�a�� �v | �M�K�t�H�g���������
��\����� CTO
|
�u�����̃��\�O���t�B�p���o��ArF�G�L�V�}���[�U�̌����J���Ƃ��̎��p���v
�@��҂�́A�����̃��\�O���t�B�p�����̌����J���Ƃ��̎��p���ɒ��N�ɂ킽����g��ł����B�܂��A�[���O���\�O���t�B�p�����Ő��E���̃C���W�F�N�V�������b�N�Z�p���������A����ɁA���E�ō����x���̌����Ƒ�o�͓����A�o�͎����ϐ��A�r�[�������萫��B�����邱�Ƃɂ��A�����̃��\�O���t�B�p���o��ArF�G�L�V�}���[�U�̊J���ɐ��������B
�@�{�Z�p�J���́A�����̃��\�O���t�B�p�G�L�V�}���[�U�̐��E�s��Ŕ����ȏ�̃V�F�A�l���������炷�Ȃǐ��������߂Ă���A���E�̔����̐����Ƃ���сA�킪���̌��Y�Ƃ̔��W�ɑ傫���v������D�ꂽ�Ɛтł���B
|
| ���{ �y�� | �M�K�t�H�g���������
���s�����@������������
|
| �`�� �O�i | �M�K�t�H�g���������
�������S������
|
| �n�� �r���Y | �������ȑ�w �������i�@�\
����
|
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
|
���� �[ | ������Ђp�c���[�U
��\������� |
�u�����x���������̗ʎq�h�b�g���[�U�̊J������ю��p���v
�@��҂�́A�\�i�m���[�g���T�C�Y�̎��Ȍ`�������̗ʎq�h�b�g�������x�E���w�E���ψ�Ɍ`�����錋�������Z�p���J�����A�Ⴕ�����l�d�������A������������A�����߂���ϐ��ȂǁA�ʎq�h�b�g�����̃��[�U�ɂ���܂Ŋ��҂���Ă������������������B����ɁA�ʎq�h�b�g���[�U�̎��p���E�ʎY���Z�p�J���𐄐i���A1.3��m�ь��ʐM�p���͂��߂Ƃ��āA���C���^�[�R�l�N�g�p�����⍂�������ł̃Z���V���O�p�����ȂǁA���ʂȉ��p����ɓW�J�����B
�@���̗ʎq�h�b�g�����̃��[�U�̊J���E���p���E�ʎY���́A��������̂��l�b�g���[�N�ɂȂ���IoT�Љ�̔��W�Ɍ��Y�Ƃ̑�����傫���v������D�ꂽ�Ɛтł���B
|
| ���� �h�O | ������Ђp�c���[�U
���s���� ���[�U�f�o�C�X���ƕ�
���ƕ���
|
| ���@���� | ������Ђp�c���[�U
���[�U�f�o�C�X���ƕ� �S������
|
��32��i2016�N�x�A����28�N�x�j
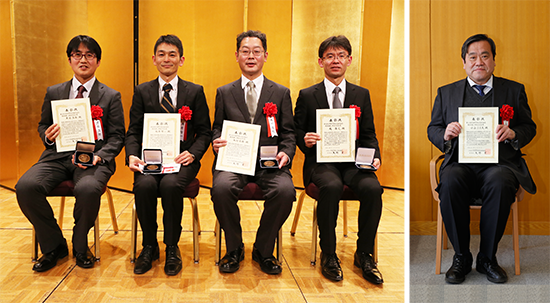
�u��32��N�䌒��Y���L�O��ҁv
�i������j���� ���Y ���A ���� �q�� ���A�ؑ� �r�Y ���A �z �_�V �� �i�E���ʐ^�j���R ��O�v ��
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
|
���� �q�� | �É͓d�C�H�Ɗ������
�����J���{��
���ʐM�E�G�l���M�[������
���� |
�u�f�W�^���R�q�[�����g�ʐM�p�������g���ό����̊J���Ǝ��p���v
�@��҂�́A�f�W�^���R�q�[�����g�ʐM�p�����̊J���Ɏ��g�݁C������DFB���[�U����Ȃ鑽�g���A���C�ƕ����̌��@�\�f�q����Ƀ��m���V�b�N�ɏW�ς��鉻�����������̋Z�p�A�]���ɔ�ׂăp�b�P�[�W�̐ς�����������ڒ��Z�p�A�����\�Ȑ���d�q��H�Z�p�̊J���ɂ��A���E�ō������̍��o�́E������̋������g���σ��[�U�����̎����ɐ��������B
�@���̋������g���σ��[�U�����̊J���E���p���́A�l�b�g���[�N�̑�e�ʉ��E���x���������炷�V�Z�p�Ƃ��Ẵf�W�^���R�q�[�����g�ʐM�̔��W�E���y�ɑ傫���v������D�ꂽ�Ɛтł���B
|
| �ؑ��@�r�Y | �É͓d�C�H�Ɗ������
�t�@�C�e�����i���ƕ���
�����̃f�o�C�X��
�ے�
|
| �z �_�V | �É͓d�C�H�Ɗ������
�R�A�Z�p�Z
��������
�����g�G���N�g���j�N�X�Z���^�[
�ے�
|
| ���� ���Y | �É͓d�C�H�Ɗ������
�����J���{��
���ʐM�E�G�l���M�[������
�ے�
|
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
���R ��O�v |
�����H�Ƒ�w
�����Y�ƋZ�p������
�����^����
|
�u�ʔ������[�U�𒆐S�Ƃ���t�H�g�j�N�X�W�ϋZ�p�̊J���v
�@��҂́A�ɉꌒ����H�Ƒ�w���_�����i��3��F1987�N�x��܁j�ƂƂ��ɁA�ʔ������[�U�iVCSEL�j�̎����A�����U��1988�N�ɐ��E�ŏ��߂ĒB�������B����ȗ��AVCSEL�̐��\����ƐV�@�\�n�o�Ɋւ��錤�����p�����AMEMS�~���[�ɂ��g�������X���[���C�g�Ȃǂ̐V�@�\���܂���VCSEL�W�σt�H�g�j�N�X�̓������B
�@����VCSEL�̌����J���́A�f�[�^�Z���^�ɂ�������C���^�[�R�l�N�g����{���̃��[�U�v�����^�Ȃǂ̋Z�p�̔��W��G�����Ă���A���Y�ƋZ�p�̐V�����W�J�ɑ傫���v������D�ꂽ�Ɛтł���B
|
��31��i2015�N�x�A����27�N�x�j

�u��31��N�䌒��Y���L�O��ҁv
�i�O�i������j�R�{ �`�T ��,���� ���W ��,���� �r�� ��,���J ���l ��
�i��i������j��� �Y�� ���C�c�� �ӏ� ���C���� �a�G ��, �ɓ� ���_ ��
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
�i�O���[�v�j
���� �r�� |
������Ѓ��R�[
���R�[�����Z�p������
�Z�t�� |
�u���[�U�v�����^�p�ʔ������[�U�A���C�̊J������ю��p���v
�@��҂�́A���[�U�v�����^�p���������̊J���Ɏ��g�݁A��������GaInPAs/AlGaInP�c�ʎq��ˍ\�������w�AAlAs��̂̍��M�`�������ˋ��A����ȃ��[�h�E�Ό������̂��߂̍������[�h�}���t�B���^�[�A�ψ�ȑf�q�����̂��߂̖ʔ������[�U�f�q���C�A�E�g�ȂǁA�Ƒn�I�ȋZ�p�̊J���ɂ��A���E�ō��o�͂���э��M���̖ʔ������[�U�A���C�̎����Ƃ��̎��p���ɐ��������B���̖ʔ������[�U�A���C�́A�v���_�N�V�����v�����^�ɓ��ڂ���A��������4800dpi�Ƃ������E�ō��̉𑜓x��B�����邱�Ƃɂ��A�V��������s������B
��҂�ɂ�鍂�o�́E���M���̖ʔ������[�U�A���C�̊J���E���p���ƁA����ɂ�鍂���E���𑜓x�v�����^�̎����A�V�K�s��̊J��E�g��́A���Y�Ƃ̔��W�ɑ傫���v������D�ꂽ�Ɛтł���B
|
| ���J ���l | ������Ѓ��R�[
���R�[�����Z�p������
�V�j�A�X�y�V�����X�g
|
| ���� �a�G | ������Ѓ��R�[
���R�[�����Z�p������
�X�y�V�����X�g
|
| �ɓ� ���_ | ������Ѓ��R�[
���R�[�����Z�p������
�V�j�A�X�^�b�t
|
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
�i�O���[�v�j
���� ���W |
�Z�F�d�C�H�Ɗ������
���ʐM���ƕ� ��� |
�u�C��P�[�u���p�ɒᑹ�����t�@�C�o�̊J���Ǝ��p���v
�@��҂�́A���E�ɐ�삯�ď��V���J�R�A�t�@�C�o���J�����A����ɂ��̃��C���[�U����ጸ���邱�Ƃɂ��A�`���������ŏ�0.149 dB/km�A����0.154 dB/km�ƁA�����A���i���ꂼ��̃��x���Ő��E�L�^���X�V�����B�{�Z�p�ɂ�萻�i�����ꂽ�ɒᑹ�����t�@�C�o�́A�����̍��ۑ�m���f���t�@�C�o�ʐM�v���W�F�N�g�ɍ̗p����A�C����ʐM�V�X�e���̐��\����ɑ傫���v�������B
��҂炪�J�������������E��e�ʓ`���ɓK�����ɒᑹ�����t�@�C�o�̎����Z�p�́A�w�����I�ɑ��傷��C���^�[�l�b�g�ʐM���v������ŕs���Ȃ��̂ƂȂ��Ă���A����̌��Y�Ɣ��W�ɑ傫���v������D�ꂽ�Ɛтł���B
|
| �R�{ �`�T | �Z�F�d�C�H�Ɗ������
���ʐM������ �卸
|
| �c�� �ӏ� | �Z�F�d�C�H�Ɗ������
���ʐM������
|
| ��� �Y�� | �Z�F�d�C�H�Ɗ������
���ʐM������
|
��30��i2014�N�x�A����26�N�x�j
 ����������, �͓c����
����������, �͓c����
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
�͓c�@��
|
����w
�@��w�@�H�w������
�@����
�����w������
�@�`�[�����[�_�[
�i�m�t�H�g���������
�@�
|
�u�v���Y�������ʂɂ�钴�𑜓x�������Ɋւ���擱�I�Ȍ����v
�@��҂́A�����i�m�\���ƃt�H�g���Ƃ̑��ݍ�p�Ɋւ�鑽���̐V�����T�O��E�����A�v���Y���j�N�X�̗̈�g��ƋZ�p�J���̓W�J��擱�����B���Ƀi�m�T�C�Y�̐�[�a��L��������T�j��p���邱�Ƃɂ��A�v���Y�������ʂɊ�Â����}���U�����̒��𑜓x�����V�X�e���𐢊E�ɐ�삯�ĊJ�������B�v���Ώۂ��A���q����i�m�����̍ޗ��A�i�m�o�C�I�ޗ��ȂǍL���W�J�����Ă���A�ٕ����Y�Ƃ֍v������Ƃ��낪�傫���B
�@�����̗D�ꂽ�����Ɛтɉ����A����ݗ������x���`���[��ƂōŐ�[�̌����Ҍ����Ƀ��}����������10�N�ȏ�ɂ킽�萻���̔����Ă���A���Y�ƋZ�p����ɂ����Ă��v�V�������炵�Ă���B
|
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
��������
|
���a�V�F�����������
�@�G�l���M�[�\�����[�V����
�@���Ɩ{���S��������
�\�[���[�t�����e�B�A
�@������Ё@���s����
|
�uCIS�����Z�p�ɂ���2 ���㔖�����z�d�r�̎��p���v
�@��҂́A�������z�d�r��1���オ�����ł��Ȃ������ϊ��������ACIS�iCuInSe2�@�J���R�p�C���C�g�n�j�������z�d�r�ɂ����Ċ����גጸ�ɗL����Cd�t���[�E���t���[�̌`�Ŏ�������ƂƂ��ɁA���Ɖ����B�������B�P����Si���z�d�r�Z�p�̐��\�ɂ��C�G������CIS�������z�d�r�́A���E�ő�K�͂�1�M�K���b�g���C���ɂăt�����ƂŐ��Y����Ă���A�\�[���[�Z��瑾�z�����d���܂ŁA�u���C�h�E�C���E�W���p���v�̔������z�d�r���ƂƂ��Đi�W���Ă���B
�@��҂炪�哱����CIS�������z�d�r�Z�p�̊J���́A�G�l���M�[���S�ۏ�A�n�����������݂̂Ȃ炸�A���d�ϊ��Z�p����̂Ƃ�����Y�Ƃ̍���̔��W�ɍv������Ƃ��낪�傫���ƔF�߂�B
|
��29��i2013�N�x�A����25�N�x�j
 ���r�v��, �e�n����,�n糌b���q��, ���ڍ��Ŏq��
���r�v��, �e�n����,�n糌b���q��, ���ڍ��Ŏq��
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
�i�O���[�v�j
�n糌b���q
|
�d�C�ʐM��w
�@���C����
|
�u�ʑ����փt�B���^��p���������Z�p�Ƃ��̃V�X�e�����̌����J���v
�@��҂́A��Љ�ŏd�v���𑝂�����摜�E����̔F���E�����̍�������ڎw���A�����Z�p�̊J��E���p�Ɏ��g�݁A�]���̑��փV�X�e�������I�ɗ��킷�邱�Ƃɐ��������B���ɁA�������p���������E�����x�̊�F�����u�ɂ����Ĉʑ����փt�B���^�v��@�̗L�����������A����ɁA�z���O���t�B�b�N���������Ƒg�ݍ��킹�Ē��ڃf�[�^�x�[�X�ɕ���A�N�Z�X����S���^�����փV�X�e�����\�z�����B�܂��V�X�e���̐M���������W�����ăN���E�h�^���挟���i���쌠�Ǘ����j�ɓK�p���A�R���e���c�Y�ƂƋ������ĐV�T�[�r�X���Ƃ̉\����T�����Ă���B�����͌��R���s���[�e�B���O���y�̓˔j�������I�ȋƐтƂ��č���̌��Y�Ƃ̔��W�ɍv������Ƃ��낪�傫���B
|
| ���ڍ��Ŏq |
���{���q��w
�@���_����
�d�C�ʐM��w
�@���C����
�������Photonics
System Solutions
�@��\�����
|
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
�i�O���[�v�j
�e�n�@��
|
��Ë@��Z���^�[
�@������
���{���[�U�[��w��
�@������
�ӂ����܈�Ë@��
�@�Y�Ɛ��i�@�\
�@������
|
�u���[�U�[�̈�É��p�Ɋւ���w�p�E�Љ�E�Y�ƊE�ɂ�����v���ƕ��y�����v
�@��҂́A���{���[�U�[��w��̊����A���[�U�[��Ë@��̊J���ƗՏ����p�ɂ����Ď哱�I�������ʂ����A��p���[�U�[���p���G���uLASER THERAPY�v�̑n���ƌ��݂ɋy�ԕҏW���s��ʂ��č����O�̃��[�U�[��Â̔��W�ɓw�߂܂����B�`���O�ȁA�畆�ȁA���`�O�Ȃł̗Տ����Â��s���ƂƂ��ɎY�w�l�ȁE���o���ȥ��ȂȂǂւ̉��p���x������e�탌�[�U�[�@��̕ێ�E���S�����w�����Ă��܂��B�܂��A���Y��p���[�U�[�@��̊J����������߂��������ƃv���W�F�N�g�Ƃ��Ĉ�H�Y�A�g������擱���Ă��܂��B���ɐ��E�ɐ�삯�ă��[�U�[��Â̐��㐧�x�y�ш��S���琧�x�̊m���ɍv�����܂����B
���[�U�[��Â̈��S�ƕ��y��g��A�@��J���ɓw�߂����Ƃ͍���̌��Y�Ƃ̔��W�ɍv������Ƃ��낪�傫���ƔF�߂܂��B
|
| ���@�r�v | ��������{��p
�@���[�U�[������
�@����
��Ö@�l�Вc�c����
�@������
|
��28��i2012�N�x�A����24�N�x�j
 �i������j���m ����, ���� ����, �R�� �x�j��, ���� ���i��
�i������j���m ����, ���� ����, �R�� �x�j��, ���� ���i��
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
�i�O���[�v�j
�R�� �x�j |
���{�d�M�d�b�������
�@�����˂��ƌ�����
�@������C |
�u������ւ��\��100G�f�W�^���R�q�[�����g���l�b�g���[�N�Z�p�̌����J���v
�@��҂́A���l�b�g���[�N�̓`���\�͂����I�Ɍ��コ����f�W�^���R�q�[�����g�����ɂ��Ĉ�g��������100Gb/s��
���`���V�X�e���𐢊E�ɐ�삯�ĊJ�������B���ɁA�`���H�̏��ێ�^�p�Ȃǎ��t�B�[���h�ւ̓K�p�ɑΉ��ł���V�X�e����
�������߂����A�v�f�Z�p�Ƃ��Č������O�v���e�N�V�����̂��߂̍����M�������Z�p�A�����Δg�g���b�L���O�Z�p�A�����
�����Z�p����єg�����U�⏞�Z�p���m�����A���������������f�W�^���M��������H�𐢊E�ɐ�삯�Ď��p�������B
�J�����ʂ́A�����Ԃ̌��ꎎ���ɂ����^�p���̖�肪�Ȃ����Ƃ𗧏��Ă���B�{�Z�p�́A���{�̗D�ꂽ���Z�p�J���͂�
���W�ɂ��傫�Ȑ��ʂƂ��āA�u���[�h�o���h�l�b�g���[�N����̐��E��擱���A����̌��Y�Ƃ̔��W�ɍv������Ƃ��낪�傫���B
|
| ���� �� | �x�m�ʊ������
�@�l�b�g���[�N�v���_�N�g
�@���Ɩ{��
�@�V�j�A�f�B���N�^�[
|
| ���� ���i | �O�H�d�@�������
�@���Z�p����������
�@���ʐM�Z�p�� ����
|
| ���m �� | ���{�d�C�������
�@�O���[���v���b�g�t�H�[��
�@�������@��������
|
��27��i2011�N�x�A����23�N�x�j
 �����K����, ���䏀����, �ɓ��O����, �e�c�v�Y��, �c���N�O��
�����K����, ���䏀����, �ɓ��O����, �e�c�v�Y��, �c���N�O��
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
|
�ɓ� �O�� | �����w������
�@�q���劲������
���k��w�@���_����
|
�u����`���w�A�e���w���c���w�̐擱�I�����v
�@�䂪���̌��Y�ƋZ�p�̊�b���Ȃ����E�ʎq�G���N�g���j�N�X�̖u����
����p�����ēƑn�I�Ȍ����Ɛт�ςݏd�˂��B�킯�Ă��A����`���w��
���������I�Ɍ��ス���߂�������ɔ��]�i�q�Z�p�������͂₭�������A
�g���ϊ��f�o�C�X�����J���̋����������Ƃ͓��M���ׂ��ł���B��
��ɁA���@����їL�@����`���w������p���������g�����ɂ��
0.5-100THz�̍L���̈�ł̃e���w���c�������ɐ������A�e���w���c���w
�Ƃ��ĂԂׂ��̈�̊�b����щ��p�����E�J���Ɏw���I�Ȗ������ʂ���
���B�ȏ�̂悤�Ɏ�҂͂˂ɐV�K�Ȓ��z�Ƃ��̎����ɒ��͂��A���
�`���w�A�e���w���c���w��擱���Ă����B���̋Ɛтƍ����ς��ʎw��
�͖͂{�܂���܂���ɒl������̂ł���B
|
| ��� | ���@�@�� | ��ܑ薼�Ǝ�ܗ��R |
�i�O���[�v�j
���� ���� |
�k�C����w
�@�d�q�Ȋw������
�@�d�q�@�\�f�q��������
�@����
|
�u�K���X�i�m�C���v�����g�@�ɂ��T�u�g���\���f�o�C�X�̊J���v
�@��҂�́A�M�����̍����K���X�ޗ��ƗʎY���E�ėp���ɗD�ꂽ�i�m
�C���v�����g�Z�p�ɒ��ڂ��A�T�u�g���\�����w�@�\�f�q�����̂��߂ɋ�
�����ĊJ����i�߂��B���Ȃ킿�A�D�ꂽ���`���ƌ��w������L����V�K
�K���X�J���A���������g���_�ɂ��v�A�ϔM�i�m���[���h�̍쐻����
�߂��C���v�����g�v���Z�X�̉��ǁA�Ɏ��g�݁A�ϔM���E�όɗD��
���T�u�g���\�����˖h�~���[���h�����Y�̍쐻�ɐ�ڂ������B�K���X
�i�m�C���v�����g�Z�p�́A�J���������Y�̔��˖h�~�\���A�Ό��q�A�g��
�Ȃǂ̌��w�@�\�f�q�ɉ����ăf�B�X�v���C�A���z�d�r�A��×p�Z���T
�[����Ȃǂւ̈�w�̓W�J�����҂���A����̌��Y�Ɣ��W�ɍv�������
���낪�傫���B
|
| �e�c �v�Y | ���{����w
�@�H�w������ �@�B�H�w����
�@����
|
| ���� �K�� | �Ɨ��s���@�l�Y�ƋZ�p����
�@�������@���r�L�^�X
�@�G�l���M�[��������
�@��C������
|
| �c�� �N�O | �p�i�\�j�b�N�������
�@�`�u�b�f�o�C�X�J���Z���^�[
�@�劲�Z�t
|
��26��i2010�N�x�j
 �i�O����j�e�r�a�N ��, �r�J���v ��,
�i�O����j�e�r�a�N ��, �r�J���v ��,
�i�����j��ݐT�� ��, �͓��R�� ��, �b��T�� ��
| �u�f�W�^���R�q�[�����g���t�@�C�o�ʐM�̌����v |
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
|
�e�r�@�a�N | ������w
��w�@�H�w�n������
�d�C�n�H�w��U
����
|
�@���t�@�C�o�ʐM�̓`���\�͂����I�ɍ��߂�ɂ͌��̈ʑ��E�U�������p����R�q�[�����g�ʐM���D�K�ł���B��҂͒��N�R�q�[�����g���ʐM�����̌����𐄐i���A�����2005�N�ɃR�q�[�����g�`�������ƃf�W�^���M��������g�ݍ��킹���u�f�W�^���R�q�[�����g�ʐM�����v�𐢊E�ɐ�삯�Ē�Ă����B�]���͌��`���H�̕��U�����Ƃ͋t�̕��U������L����Z�ڌ��t�@�C�o�Ȃǂ�p���镪�U�⏞�������p����ꂽ���A��҂͎�M�M���̒����Q������Ɨ��Ɏ�M������Ƀf�W�^���M���������s���ĕ��U�⏞����f�W�^���R�q�[�����g�ʐM����������̒��������ʐM�̖{���Ƃ��Ē�āE�������B���݁A���E���Ŗ{���������̂��߂̒������f�W�^�������f�o�C�X�ȂǂɊւ��錃��ȊJ���������n�܂��Ă��邪�A���̐��҂Ƃ��Č��Y�Ɣ��W�ɍv������Ƃ��낪�傫���B
|
| �u�u���[���C�f�B�X�N�p PTM���Ս쐻�Z�p�̊J���Ƃ��̎��p���v |
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�i�O���[�v�j
�r�J�@���v |
�\�j�[�������
�R�A�f�o�C�X�J���{��
�ے�
|
�@��҂�́A����܂œd�q���`�摕�u���K�{�Ƃ���Ă����u���[���C�f�B�X�N���Օ`��H���̑���ɁA�V�����J�������q�[�g���[�h���@���W�X�g�ޗ��ƐF���[�U��g�ݍ��킹��Phase Transition Mastering (PTM)�Z�p�Ƃ������Y���ɗD�ꂽ���Ս쐻�Z�p�����������B
�@�d�q���`�摕�u��K�v�Ƃ��Ȃ��{�����ɂ�錴�Ս쐻�V�X�e���̎��p���ɂ��u���|���C�f�B�X�N�̗ʎY���i�W���A�u���[���C�f�B�X�N���}���ɐ��E�ɕ��y�����B��N�x�A�S���E�Ő������ꂽ�S�����̓��f�B�X�N�̂����A���̑唼���{�����ɂ����̂ł���B�Ȃ��A����PTM�Z�p�͔����H�Z�p�Ƃ��Ă̓W�J������A����̌��Y�Ɣ��W�ɍv������Ƃ��낪�傫���B
|
| �͓��R�@�� | �\�j�[�������
�R�A�f�o�C�X�J���{��
|
| �b��@�T�� | �\�j�[�������
�R�A�f�o�C�X�J���{��
�ے�
|
| ��݁@�T�� | �\�j�[�C�[�G���V�[�G�X
�������
�R�A�Z�p����
�ے�
|
��25��i2009�N�x�j
 ���� �� ��,��ؐ��q ��,�c���p�� ��,���_�T�� ��,���蓿�� ��,���{�F�� ��
���� �� ��,��ؐ��q ��,�c���p�� ��,���_�T�� ��,���蓿�� ��,���{�F�� ��
�u�ΐF�悩�率�O���GaN�n�����̃��[�U�����A�����U�v
|
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�O
��
�b
�v |
���_�@�T�� | �������w�H�Ɗ������
�J���{��
�����������̌�����
�劲������
|
�@��҂̓��C�h�M���b�vGaN�n���[�U�̉\�������߂�ׂ��J��������]�ʖ��x�E����������̍쐬����э��i�����d�ʎq��ˍ\�������̓Ǝ��Z�p��˔j���ɁA�ΐF�悩�率�O��̍L���g���͈͂ɂ킽��i�g��365 nm�|515 nm�j�����̃��[�U�����������B���ɘA�����U�ΐF�����̃��[�U�̎����A�F�����̃��[�U�̗ʎY���A�Y�Ɨp���o�̓��[�U���W���[���i10 W�j�Ȃǂ̐��i���ɍv�������B�g���͈͂̊g��A���o�͉��A���M�����ɂ��K�p�͈͂̓f�B�X�v���C�p�A���L�^�p�A��ÁE�o�C�I���p�Ȃǂւ̈�w�̓W�J�����҂���A����̌��Y�Ɣ��W�ɍv������Ƃ��낪�傫���B
|
| ����@���� | �������w�H�Ɗ������
�J���{��
�����������̌�����
��C������
|
| ���{�@�F�� | �������w�H�Ɗ������
�J���{��
�����������̌�����
��C��������
|
�u���M���x��m���f���C��P�[�u���V�X�e���̎��p���v
|
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�O
��
�b
�v |
�c���@�p�� | �������KDDI������
���s����
|
�@��҂́A�������ʐM�V�X�e���ɕK�{�̒�`���[�v�E��������̗D�ꂽ������L����t�����c�P���f�B�V���^�d�C�z���ϒ���Ȃǂ��J�����A�������ɂ߂č����M�������v��������e�ʑ�m���f���C��P�[�u���V�X�e���֓K�p���邱�Ƃ��������A���ߍ��ݍ\�����̗̍p�A���ϒ���̓�������̖��m���Ȃǂɉ�����9000 km�̑�K�͎���������9�N�Ԃ̎��p�T�[�r�X���o�āA���t�B�[���h�Ō̏ᗦ13.8�iFIT�j�ȉ��Ƃ����ɂ߂č����M�������������B�����̐��ʂ́A���M���x�̌��ϒ���̊J���ɂƂǂ܂炸�A��e�ʍ��ےʐM�l�b�g���[�N�̍\�z�ɍv������Ƃ��낪�傫���B
|
| ��@���q | �������KDDI������
���s����
|
| �����@�T�� | �Ɨ��s���@�l
���ʐM�����@�\
����
|
| �����@�� | ���{�q��d�q�H��
�������
�ږ�
|
��24��i2008�N�x�j

�@�@�@�@�F�s�{ �� ��,�@�@�@�@�ѓc���� ��,�@�@�@�c���a�u ��,�@�@�@�ɓ��G�B ��,�@�@�@�@������� ��
|
�uBlu-ray Disc�p�����\�n�[�h�R�[�g�Z�p�̊J������ю��p���v
|
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�O
��
�b
�v |
�F�s�{ �� | TDK�������
SQ�������@�劲
|
�@�V����̌��f�B�X�N�̋K�i��2008�N���X��Blu-ray Disc(BD)�Ɍ��������BBD�p���f�B�X�N��25GB�̑�e�ʂ��������邽��1.1mm���̃|���J�[�{�l�[�g��\�ʏ�ɁA0.1 mm���̔����ی�w�Ƃ��̒����̋ɔ��L�^�w���݂����Ă���B����́A�ی�w�̔������f�B�X�N�́A�w��t����\�ʏ��Ɏア�Ƃ�����������Ă����B
�@�����ŁA�V���J�����q���܂ލ����\�n�[�h�R�[�g�Z�p���J�����A���f�B�X�N�\�ʂɏ���w��i����j�ɑ��āA���d�x���h�������ɗD�ꂽ�ی�w��݂��邱�Ƃɐ��������B���̌�����v�ŏ]�����x���𗽉킷��w��ϐ����тɎC�ߏ��ϐ������ی�w�`���Z�p�̎����ɂ��A�ی�W���P�b�g�s�v�̌o�ϐ��ɗD�ꂽ��e�ʂ�BD�p���f�B�X�N�����p�����ꂽ�B
|
| �ѓc ���� | TDK�������
SQ�������@������C
|
| �c�� �a�u | TDK�������
SQ�������@��C������
|
| �ɓ� �G�B | TDK�������
�f�o�C�X�J���Z���^�[
������
|
�u�}�C�N���ő̃t�H�g�j�N�X�̐��I�����v
|
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
���� ��� | ��w�������p�@�֖@�l
���R�Ȋw�����@�\
���q�Ȋw������
�y����
|
�@�ő̃��[�U�[�̎��p���ɕs���ȏ��^���A�����\����}�邽�߁A���[�U�[�}���̃}�C�N���h���C���\�������A�E�ʐ���ɂ��V���ɔ����������w�@�\��T�����A�u�}�C�N���ő̃t�H�g�j�N�X����v��n�o�A�擱���Ă����B���ɁA�����\���E���o�͉�����������C�b�e���r�E���E�Z���~�b�N�X�ɑ�\�����}�C�N���`�b�v���[�U�[�̐��E�ɐ�삯����Ă���ю����ƁA�o���N�[���ʑ������f�q�ɂ�鍂�o�͔���`���w�g���ϊ����������A������̊�Ս\�z�ƓW�J�ɑ傫����^�����B�����̐��ʂ́A�Y�Ɗ�Ղ��x�����{�I�v������H���u�ɕs���ȁA���O����ԊO�Ɏ���}�C�N���R�q�[�����g�����̎��p�ɋ������ȂǁA����ȍv�������Ă���B
|
��23��i2007�N�x�j

| �u�N���ҋL�O�ʐ^�����v |
�i�O����j
�쐼�N�� �� �i(��)���ʐM�����@�\�j
�䓛��V �� �i(��)���ʐM�����@�\�j
����`�� �� �i������w�j
�{�{�@�T �� �i���{�d�M�d�b(��)�j
�x�V���l �� �i���{�d�M�d�b(��)�j
|
�i�����j
���G�@�O �� �i�Z�F���Z�����g(��)�j
�s�쏁��Y �� �i�Z�F���Z�����g(��)�j
���c�_�� �� �i���{�d�M�d�b(��)�j
�����L�� �� �i���{�d�M�d�b(��)�j
|
�u���������l�b�g���[�N�����n�s�m�f�W�^���t���[���̍��ەW������
���l�ʑ��ϒ������̌����J�����p���v |
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�O
��
�b
�v |
�{�{�@�T | ���{�d�M�d�b�������
�����˂��ƌ�����
|
�@���l�b�g���[�N�̂���Ȃ��e�ʉ��A�o�ω��̂��߂ɁA40Gb/s�ȏ�̍����`���ɓK����OTN�f�W�^���t���[���\���𐢊E�ɐ�삯�Ē�Ă��A���ەW���iITU-TG.709�����j����ɒ��S�I�ȍv��������܂����B
�܂��A40Gb/s�̒������`���ɓK�����q�y�p���X���S�l�����ʑ��ϒ����`���������J�����A���E����40Gb/s�g�����d���`�����������p������܂����B����ɁA�������x�[�X�Ƃ���100G�C�[�T�l�b�g���������̒������`���Z�p���Ă��A���ەW�����ɂ�������{�̎哱���m�ۂɑ���ȍv�������ꂽ�B
|
| �x�V�@���l | �����{�d�M�d�b�������
�����˂��ƌ�����
|
| ���c�@�_�� | ���{�d�M�d�b�������
�t�H�g�j�b�N������
|
| �����@�L�� | ���{�d�M�d�b�������
�l�b�g���[�N�T�[�r�X
�V�X�e��������
|
�u�W�ό��ϒ��f�o�C�X�ɂ�鍂�����ʑ��E���g���ϒ��Z�p�̊J���v
|
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�O
��
�b
�v |
�䓛�@��V | (��)���ʐM�����@�\
|
�@�W�ό^�j�I�u�_���`�E����p������P���єg�����̐i�s�g�^�ϒ��f�o�C�X����O�ɐ�삯�Ē�āE�����A����ɍŋ߂̊e�퍂�����l�ϒ����ɂ�����܂Œ��N�ɂ킽���т��Ă��̊J����擱���A���̐U���A�ʑ��A���g��������������ɕϒ����邱�Ƃ��\�Ƃ���܂����B���̋Z�p�́A����e�ʓ`���A�`���g�`�⏞�A�����ʑ��ϒ��ȂǁA����̌��l�b�g���[�N�\���̒��j�ƂȂ�Z�p�ł���A��������ʐM����̌����J���ɑ���ȍv�������ꂽ�B
|
| �쐼�@�N�� | (��)���ʐM�����@�\
|
| ���G�@�O | �Z�F���Z�����g(��)
|
| �s��@����Y | �Z�F���Z�����g(��)
|
�u�t�H�g�j�b�N�l�b�g���[�N�p�����E��d�͏W�ό��f�o�C�X�̊J����
�v�V�I�T�u�V�X�e�����v |
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
����@�`�� | ������w
����
|
�@������t�H�g�j�b�N�l�b�g���[�N�ɓK����V�K�����E��d�͏W�ό��f�o�C�X���āE�J�������ƂƂ��ɁA�V�O���ȏオ�Q�悵�������L�͊�ƂƂ̎Y�w�A�g�v���W�F�N�g�ɂ����đ�z�������[�_�[�V�b�v������A��w�l�Ƃ��Ă̐V�������݊��������Ȃ��炱���̗L�p��������������x�������p�P�b�g���[�e�B���O�̃V�X�e���f�����X�g���[�V�����𐢊E�ɐ�삯�Đ����ɓ����A��������ʐM����̌����J���ɑ���ȍv�������ꂽ�B
|
��22��i2006�N�x�j
 �@�@�@�@�@�c���F�j ��,�@�@�ɓ��ꖱ����,�@�@�c���ψ���,�@�@�@���c�卸, �@�@�@�O�� �� ��
�@�@�@�@�@�c���F�j ��,�@�@�ɓ��ꖱ����,�@�@�c���ψ���,�@�@�@���c�卸, �@�@�@�O�� �� ��
(��O)���O�� ��, �������I ��
| �uFTTH�̂��߂̌��A�N�Z�X���H�E�H�@�E�V�X�e���֘A�����Z�p�̌����J���v |
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�O
��
�b
�v |
���@�O�� | ���{�d�M�d�b�������
�A�N�Z�X�T�[�r�X�V�X�e��������
����
|
�@�ʐM���Ǝ҃r�����烆�[�U��Ɏ�����t�@�C�o���H���A���\��o�ϐ��ɉ��������Ɛ��Ȃǃq���[�}���t�@�N�^���܂ߑ����I�Ɍ����J�����A�����H�ݔ��̑�K�͌��݂Ɖ^�p�����������B�X�ɁA�F�A�Í�����ێ�ȂǃL�����A�O���[�h�̌��A�N�Z�X�V�X�e�����J�����A���S���S�ȑo�����u���[�h�o���h�A�N�Z�X�T�[�r�X��\�Ƃ����B�����̑����I��FTTH�Z�p�ɂ��A���{�͐��E�ɐ�삯�{�i�IFTTH������}������B
|
| �����@���I | �����{�d�M�d�b�������
�Z�p��
���ێ���
|
| �c���@�F�j | ���{�d�M�d�b�������
�A�N�Z�X�T�[�r�X�V�X�e��������
�劲������
|
| �O��@�� | ���{�d�M�d�b�������
�A�N�Z�X�T�[�r�X�V�X�e��������
�劲������
|
��21��i2005�N�x�j
 �@�@�@�א쑬�� ��,�@�@�@�@�@�@���� �G ��,�@�@�@�@�@���X�؍F�F ��,�@�@�@�@�X �E�� ��, �@�@�@�א�z��Y �� �@�@�@�א쑬�� ��,�@�@�@�@�@�@���� �G ��,�@�@�@�@�@���X�؍F�F ��,�@�@�@�@�X �E�� ��, �@�@�@�א�z��Y ��
| �u�|���}�[�����g�H�̊J���Ǝ��p���v |
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
|
�א�@���� | �I�������������
�@�Z�p�{��
�@��[�f�o�C�X������
�@SPICA���i�O���[�v
�@�O���[�v���@�劲
|
�@�i�m�C���v�����g(����)�@�̉��H���x�A���R�������߂邱�ƂŒᑹ���̃|���}�[�����g�H���쐻����Z�p���J�����A���^�𗘗p��������g�H�̑�ʐ��Y�A��R�X�g���ɓ�����B�K�p�ΏۂƂ��Č��A�N�Z�X�n�p�����i�A���@����̌��z���𐄐i����ق��A����o�C�I����ł̌��v���A���C���^�[�R�l�N�V�������ւ̓W�J���L�]�ł���A���Y�Ƃ̔��W�ɑ���d�v�ȍv���ƔF�߂���B
|
| �u�t�F���g�b���[�U�p���X�ɂ��`�����̌������v |
|---|
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�O
��
�b
�v |
�����@�G | ����w
��w�@�H�w������
�����Ȋw�E���p�����w��U
����
|
�@���[�U�[�A�u���[�V�����̕����w�I�����y�ѕ��q�_�I���J�j�Y���̌����ƁA��ߖO�a�n�t���ł̗L�@�����j�̔������䌤���̐��ʂɊ�Â��A���o�̓t�F���g�b���[�U�p���X��`�����n�t�ɏW�����邱�Ƃɂ�茋������}��S���V�������@���l�Ă��A�`�����̍��i���Ȍ������ɏ��߂Đ��������B�l�̈�`�q�𖾂͂قڏI�����A���l�Ȓ`�����̍\����́E�@�\�̉𖾂��Ŕ��̖��ƂȂ��Ă��錻�݁A�{�����̓��[�U�[�̃o�C�I���p�ɐV���ȓ����J�Ă���A�`�����̌�����͂�ʂ��Đ����Ȋw����ɑ傫�ȃC���p�N�g��^���Ă���B
|
| ���X�@�F�F | ����w
��w�@�H�w������
�d�C�d�q���H�w��U
����
|
| �X�@�E�� | ����w
��w�@�H�w������
�d�C�d�q���H�w��U
������
|
| �א�@�z��Y | �i�Ɓj�Ȋw�Z�p�U���@�\
�헪�I�n���������i����
������
|
��20��i2004�N�x�j

| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�O
��
�b
�v |
���� �`�� | �������w�H�Ɗ������
�@���Z�p��
�@�Z�t�� |
�u���F�����_�C�I�[�h�̔����Ǝ��p���v
�FLED�`�b�v��ɍL�g���攭���X�y�N�g����L����YAG���F�u���̂�h�z�����������E���o�́E�����F���̔��F�����_�C�I�[�h���J�����A�g�ѓd�b���܂މt���\�����u�̃o�b�N���C�g���̋���ȐV�s���Z���Ԃɑn�o�����B�F���x�̐�����\�ł���A�������ő̏Ɩ������Ƃ��Ẳ\���������A���\�I�ɂ���ɐ��E�����[�h���A�o�ώЉ�I�e��������߂đ傫���A���Y�Ɣ��W�ɑ���ȍv���������B
|
| ��� ���� | �������w�H�Ɗ������
�@���Ɗ�敔�@���Y�Ǘ���
�@�ے� |
| ��� �� | �������w�H�Ɗ������
�@���Z�p���@��O��
�@�ے��㗝 |
| �X�� �q�� | �������f�o�C�X�������
�@����������
�@�ے� |
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�O
��
�b
�v |
�֓c �m�u | �T�C�o�[���[�U�[�������
�@��\������@�� |
�u�t�F���g�b�ő̃��[�U�[����ѐ[���O�������ő̃��[�U�[�̎��p���v
�t�F���g�b�ő̃��[�U�[����ѐ[���O�������ő̃��[�U�[�ɂ����āA�����艻���[�U�[���U��A���t�@�C�o�[�ڑ��A��N�����̂�Q�X�C�b�`�̘A���A��������@�\�̋Z�p�m���ɂ�荂����E�������E���o�͂��������A�Y�Ɨp�ɗe�Ղɗ��p�\�ȃ����e�i���X�t���[�������߂��Y�Ɨp���[�U�[���u�����p�����A�����̎Y�Ɖ��p�g��ɍv�������B
|
| �Z�g �N�� | �T�C�o�[���[�U�[�������
�@������@���� |
| ���� ��� | �T�C�o�[���[�U�[�������
�@�J�����@���Z�p�ے� |
| ���v�� �� | �T�C�o�[���[�U�[�������
�@�������@��Ȍ����� |
��19��i2003�N�x�j

| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�O
��
�b
�v |
����@�N�v | ��B��w
�@��w�@���H�w�����@
�@���� |
�u�L�@EL(electroluminescence)�Ɋւ����b�����y�т��̎��p���v
�L�@EL�Ɋւ��āA���F�������������鐳�E�A���w�^�����w�^�d�q�A���w���琬��_�u���w�e���\���̒Ɠ���@�\�̉𖾁A����������������ӌ��ޗ��̒Ǝ��A�h�[�p���g�̒�Z�x����ɂ��RGB���������ɂ�锒�F�����̎��A�����h�[�v�ɂ�锭�������̌���A�ޗ��̕�ނ�h�[�p���g�̌����J���A�f�B�X�v���C�p�����׃h�b�g�p�^�[���j���O�Z�p�╕�~�Z�p�A�����쓮���@�ȂǁA�����̏d�v�Ȍ����J�����s���A�ԍڗp�y�ьg�ѓd�b�p�f�B�X�v���C�𐢊E�ɐ�삯�Ď��p���ɐ��������B�����́A�ߔN�����ƂȂ��Ă��鎟����f�B�X�v���C�J���̊�b�𐬂��Ă���A���G���N�g���j�N�X����ւ̍v���������]���ł���B
����A�{�Ɛт���ɁA��^�f�B�X�v���C�̑��A�NJ|TV��y�[�p�f�B�X�v���C�Ȃǂ̊J���ɂ��A�f�B�X�v���C�Y�ƂȂǂ̔��W�Ɋ�^���邱�Ƃ����҂����B
|
| ��ˁ@�~�� | �R�`��w�@�H�w��
�@���� |
| ���c�@�@�m | �p�C�I�j�A(��)
�@�����������@
�@�\���f�o�C�X������
�@���� |
| �c���@�ƕv | ���k�p�C�I�j�A(��)
�@�햱���s���� |
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�O
��
�b
�v |
�����@�@�� | ���{�d�M�d�b�i���j
�@�A�N�Z�X�T�[�r�X
�@�V�X�e��������
�@�劲������ |
�u���t�@�C�o�Ђ��v���Z�p�̌����ƊJ���v
���t�@�C�o���̃u�����A���U�����t�@�C�o�ɐ����Ă���Ђ��݂ɂ���Ď��g���V�t�g���邱�Ƃ𗘗p���A�p���X�����������[�U���̎��g���V�t�g����Ђ��݂̑傫�������߂�ƂƂ��ɁA����U�����̖߂莞�Ԃ��炻�̏ꏊ�����߂邱�Ƃɂ��A�\�����̂Ђ��݂����t�@�C�o�̒��������̕��z�Ƃ��Čv������Z�p���J�������B�܂��A�g���l����͐��h�A�A�����J�Y�J�b�v�̃��b�g�Ȃǂ̃��j�^�����O��ʂ��āA�{�Z�p���\�����̂Ђ��݂��v��������@�Ƃ��ėL���ł��邱�Ƃ��������B���݁A�{�Z�p�͓y�،��z����q��F���ɂ킽��\�����ɂ����p����ABOTDR�iBurillouin Optical Time Domain Reflectometer�j�Ƃ��Ēm���Ă���B�{�O���[�v�����t�@�C�o��p�����\�����Ђ��v���̕������I�ɊJ�����Ƃ͍����]���ł���B
����A�{�Z�p�́A�\�����̈��S���]���̕���A�\���������̕���̔��W�ɂ���^������̂Ɗ��҂����B
|
| �q���@���Y | ���{�d�M�d�b�i���j
�@�A�N�Z�X�T�[�r�X
�@�V�X�e��������
�@�劲������ |
���@���d
�i�̐l�j | ���@���{�d�M�d�b�i���j
�@�A�N�Z�X�T�[�r�X
�@�V�X�e�������� |
��18��i2002�N�x�j

| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
|
��c�@�i |
���s
��w�H�w������ ����
|
�i�m�����\���ɉ��H���������̃E�G�n��Z���ϑw����V�K�ȕ��@�Ō��g���тœ���\�Ȋ��S�R�����t�H�g�j�b�N�o���h��������������ƂƂ��ɁA���ׂ̓����ɂ�������Ȃǂ̉𖾂��s�����B�܂��A�ʓd�\�ȓ��������āA�Q�����t�H�g�j�b�N�����ɂ��}�C�N���f�B�X�N�����̃��[�U���͂��߁A�����^�̊e��̌��f�o�C�X�������J�������B�{�Ɛт́A����̍��@�\���f�o�C�X�����̉\���������A�T�C�G���X�ƌ��G���N�g���j�N�X�̐ړ_�Ƃ��Ă����ڂł�����̂ŁA�����̌��h�s�Y�Ƃ̔��W�ɑ傫���v�����邱�Ƃ����҂����B
|
�i�O���[�v�j
�A�c ����
���J ����
|
�d�C�ʐM��w
���[�U�[�V���㌤���Z���^�[
�Z���^�[���@����
�_�����w�H�Ɗ������
�Z���~�b�N�X���ޗ��J����
�ے�
|
�i�m���������Č�������@�ɂ��A�]���A�s�\�ł��������������E�ł̎U���v�f�����ȏ��ł����āA�����ߐ��̗D�ꂽ�Z���~�b�N�̐V�K�Ȑ����Z�p���m�������B�{���@�ɂ��A�Z���~�b�N�x�`�f���b�h�ŒP�������b�h�����鍂�o�̓��[�U���U�����������B�{�Ɛт́A�P�����ő̃��|�U�ł͌��E�������^���Ɛ��䐫�̌��E��ł��j���đ�o�͉����\�Ƃ�����̂ŁA�ő̃��|�U�̏�����h��ւ����B����A���o�́A�Y�Ɨp���[�U����ł̍v�������҂����B
|
��17��i2001�N�x�j

| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�i�O���[�v�j
�l�c�b���q��
���@���� |
���z�U�d�������
�@���Ɛ헪��敔
�@��Ȍ�����
�@�H�w���m
����
�@CD-R�̌����ɏ]���B
|
�����ܗ��A��z���W����L����F�f�ɂ��L�^�w�Ɋ��\�����`������Ƃ�������I���z�ŁACD�Ɗ��S�݊�����L����L�@�F�f�g�p�̋L�^�\CD(CD-R)���J���A�o�ϐ��ɗD�ꂽ��e�ʋL�^�}�̂��\�Ȃ炵�߁A���̕���̐��E�I�W���Z�p�Ƃ���CD-R���g�̕��y�݂̂Ȃ炸�A���Y�Ǝs��g��ɑ���ȍv���������B
|
�i�O���[�v�j
����H�F��
�ɒn�m�N�N��
�r��Èꎁ
|
�É͓d�C�H�Ɗ������
�@���l������
�@�����̌����J���Z���^�[��
�@��WA�`�[�����B �H�w���m
����
�@�t�@�C�e�����i���ƕ�
�@���f�o�C�X���@�����⍲
����
�@�t�@�C�e�����i���ƕ�
�@���f�o�C�X���@�����⍲
|
���t�@�C�o������̗�N�p���[�U�i�g��1480 nm �����980 nm�j�Ƃ��āA�Ǝ��ɐv�����c�⏞�^�ʎq��ˊ����w�����A�������ׂ̏��Ȃ����Y���ɗD�ꂽ���������@���m�����Đ��E�ō��̍��o�͓���ƗʎY���������A�g�����d(WDM)�Z�p��p������e�ʌ��t�@�C�o�ʐM�V�X�e���̔��W�E���y�ɑ���ȍv���������B
|
��16��i2000�N�x�j

| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
| ���@����Y�� |
���k��w
�@�����Ȋw�Z�p
�@���������Z���^
�@�q������ |
�����I�\����L����t�H�g�j�b�N�����̏d�v���ɒ��ڂ��C�����̋Z�p�����p�����Ǝ��̑��w�����Z�p(���ȃN���[�j���O�@)���J���C����ɂ��̑傫�Ȕg�����U����ٕ������̓����𗘗p������t�B���^�C�����g��C�Ό��f�q���̐V�������p�����C�����㒴���^���f�o�C�X���̌����J���ɑ���ȍv���������B
|
�i�O���[�v�j
�v�ۓc�d�v��
�����q�Y��
�]�����Ǝ�
�c���K�ꎁ |
�\�j�[�������
���s����
�R�A�e�N�m���W�[&
�@�l�b�g���[�N
�@�J���p�j�[�E
�@�R�A�e�N�m���W�[
�@�J���{���E
�@�v�ۓc������
�@��C������
V-S2Project
�@��C������
�R�A�e�N�m���W�[&
�@�l�b�g���[�N
�@�J���p�j�[�E
�@�R�A�e�N�m���W�[
�@�J���{���E
�@�v�ۓc�������@�ے�
�@ |
�x�[�^��_�o���E���P�����琬�v���Z�X�̉��P�C�������d���A�N�`���G�[�^���܂ތ����U��T�[�{�@�\�̊J���ƌ��w�p�����[�^�̍œK���ɂ��C�����̃��[�U��NNd-YAG���[�U��p����O�����U��^��l�����g�������u���J�����C���肩�M�����̂���A���o��30mW�̎��O�g��266nm�̌����������C���f�C�X�N�┼���̐������쓙�ւ̎Y�Ɖ��p�ɑ���ȍv���������B
|
��15��i1999�N�x�j

| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
| �ΐ쐳�r�� |
������w��w�@
�@�H�w�n������
�@�v���H�w��U |
����d�q�Z���ɂ���������ь��C���^�R�l�N�V�����̗L��������A�\�V�A�g�����,����d�q����}�V�����������SPE-�U��⢒���������r�W�����`�b�v����̐�i�I�V�X�e���̎����ɂ���Ė��炩�ɂ�,������Z�p�̌����J���ɑ���ȍv���������
|
�i�O���[�v�j
���c���Y��
���菟�㎁
���씎�V�� |
�����}�N�Z���������
�@�}�g������ |
�����C�f�B�X�N�̍����x������������Z�p�Ƃ��đ��l�L�^,����g��Đ������MAMMOS����,����ɂ��n�[�h�f�B�X�N���z�����e�ʉ��ւ̓����������Ƃ�,�����������Z�p�̌����J���ɑ���ȍv���������
|
��14��i1998�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
| �r��וF�� |
������w
�@�����E�H�w���m
�@��[�Z�p�����Z���^ |
�ʎq��˔����̃��[�U�̌����I�L�]����\�����A����ɁA����������ʎq�א���ʎq�h�b�g�\���ɂ��������P�ƃ~�N���Ȕ����@�\�]���̐V������@���J�A���ʐM�p�����̃��[�U�̌����J���ɑ���ȍv���������B
|
�i�O���[�v�j
���r������
�c�@���� |
�L����w
�@�H�w��������
(��)�x�m�ʌ�����
�@�y���t�F�����V�X�e��
�@�������@��nj����� |
ADDRESS DISPLAY SEPARATION(ADS)����
�ɂ��t���J���[���Ԓ��\���Z�p��MgO�ی얌��p������d���쓮�����ɂ�钷�������Z�p���J�����AAC�^PDP�̎��p���ɑ���ȍv���������B
|
��13��i1997�N�x�j
 
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
�i�O���[�v�j
���ˈ�v��
���X�ؒB�玁
�����[�Y��
�R�����K�� |
���{�d�C(��)
�@����������g�f�o�C�X���������㗝
���@���E�������g�f�o�C�X������
�@���f�o�C�X�������������ے�
���@�t�k�r�h�f�o�C�X�J��������
�@���f�o�C�X�J�����v���W�F�N�g
�@�}�l�[�W���[
���@���E�������g�f�o�C�X������
�@���f�o�C�X�������������ے� |
���U�g���̈قȂ鑽���̔����̃��[�U���P���̃E�F�[�n��Ɍ`�����鎖���\�ɂ���A�����I���l�n�u�o�d�����Z�p�̊J���ɂ��A�g�����d���ʐM�V�X�e���p�L�[�f�o�C�X�����J���ɑ���ȍv���������
|
�i�O���[�v�j
�{�����ꎁ
��Α䎁
�R�c�@����
���X�Ǝ��� |
NTT���G���N�g���j�N�X������
������敔��
���@�ޗ��������t�@�C�o�A���v�ޗ�
�@�����O���[�v�O���[�v���[�_�[
���@�ޗ��������t�@�C�o�A���v�ޗ�
�@�����O���[�v��C������
���@�ޗ��������t�@�C�o�A���v�ޗ�
�@�����O���[�v�劲������ |
�]���̑ш敝��傫������e�����C�g�n�K���X�ޗ���p�������L�ш���t�@�C�o��������J�����A���ʐM�V�X�e���y�уl�b�g���[�N�̌����J���ɑ���ȍv���������B
|
��12��i1996�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
| �r��O�F�� |
NTT�A�h�o���X�e�N�m���W(��)
�@��\������� |
���Z�p�ɌW��鍑�ۊw��C���ەW���������ɂ����Ďw���I�������ʂ����ȂǁC���E�I����ɂ������������悲���f�o�C�X�̌�����ʂ��C���Y�Ƃ���ь��Z�p�̐U���ɑ���ȍv���������B
|
| ���r�N���� |
�c��`�m��w
�@���H�w�����p�Ȋw��
�@������ |
���O�ɐ�삯�ĊE�ʃQ���d���@����ёS�t�b�f���|���}�[�ɂ��W���^�L�ш�ᑹ���v���X�`�b�N�t�@�C�o���������C���ʐM�̍���̍L�͈͂ȉ��p���\�Ȃ炵�߂��B
|
��11��i1995�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
(�O���[�v)
�쐼��
���ǏG�F��
�����q�v��
���n���r�� |
NTT���l�b�g���[�N
�@�V�X�e��������
�@������������
�@�����O���[�v
�@��C������
���@������������
�@�����O���[�v
�@������C
���@������������
�@�����O���[�v
�@��C������
���@������������
�@�����O���[�v
�@�O���[�v���[�_ |
�d�C�M�������̌��E���z���钴�������ʐM�Z�p�̎�����ڎw���C�X�[�p�[�R���e�B�j�E�������A�S�����������d�����Z�p�C���^�C�~���O���o�Z�p���̐V�Z�p���J�����邱�Ƃɂ��C�S�����������d���������ɂ��200G�r�b�g�M����100km�`�������ɐ������A�������M���`���E�����Z�p�̐V���ȉ\�����������B
|
(�O���[�v)
�����Ljꎁ
�|�i�r����
���R���v��
����F�O�� |
�����d��Y��(��)
�@���f�B�X�N���ƕ�
�@���J���v�@�Q��
���@���f�B�X�N�J���Z���^�[
�@��搄�i�O���[�v
�@��S��
���@���f�B�X�N�J���Z���^�[
�@�f�o�C�X�J���O���[�v
�@��S��
���@���f�B�X�N�J���Z���^�[
�@�f�o�C�X�J���O���[�v
�@���Q�� |
�����\���ω����f�B�X�N��CD-ROM���f�B�X�N�Ƃ�h���C�u�ŏ����ł���V�Z�p����O�ɐ�삯�ĊJ�����C���f�B�X�N�̔��W�ɑ���ȍv���������B
|
��10��i1994�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
(�O���[�v)
�����C��
����F�u��
������V�� |
�������w�H��(��)
�@���
�@�J�����@�劲������
���@���@�Z�p��
�@���ہ@���W�@�W��
���@���@�J����
�@���O���[�v�@��C |
MOCVD�@��p�������������Z�p�ɓƑn�I�ȍH�v�������邱�Ƃɂ��C��������������I�ɍ���GaN�n�������J�����C���ޗ���p���č��P�x�̐F�����_�C�I�[�h�̎��p���ɐ��������B���̋Z�p�J���ɂ��LED�ɂ��t���J���[�\�����\�ɂȂ�ȂǁC���̔g�y���ʂ͑傫���B
|
| �͓����v�� |
���{�d�M�d�b(��)
�@NTT���G���N�g���j�N�X
�@������
�@���������i
�@�������� |
���t�@�C�o�����Z�p��LSI�����H�Z�p�Ƃ̗Z���ɂ��C�V���R�����ɒᑹ���ȐΉp�n�����g�H���`�����C���A�N�Z�X�Ԃ̍\�z�Ɍ��������^���J�v�����玟����̌��g�l�b�g���[�N���������ڎw�������g�������g���}�g���N�X���X�C�b�`�Ɏ��鑽�ʂȕ��ʌ���H�����������B
|
��X��i1993�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
(�O���[�v)
�p�c�`�l��
�O�c���u��
�d���a�j�� |
(��)�������쏊
�@����������
(��)�������쏊
�@����������
(��)�������쏊
�@�X�g���[�W�V�X�e�����ƕ� |
�}�[�N�G�b�W�L�^���������f�B�X�N�ɏ��߂ēK�p���C���f�B�X�N�̋L�^���x���Q�{�ȏ�Ɍ��コ���C��������f�B�X�N�̐i�W�C�W�����ɍv�������B
|
(�O���[�v)
�����[��
����@����
�R�����u�� |
(��)�x�m�ʌ�����
�@�}���`���f�B�A
�@�V�X�e��������
�@�e�N�m���W��������
�@��nj�����
(��)�x�m�ʌ�����
�@�p�[�\�i���V�X�e��
�@������
�@�f�o�C�X��������
�@���f�B�A�f�o�C�X������
�@��C������
�x�m��(��)
�@��ʐM���Ɩ{��
�@���J�����i��
�@���J����
�@��O�Z�p�� |
��A��Ti:LiNbO�R���g�H�f�o�C�X�̌����̖��C���x�h���t�g�y��DC�h���t�g�̖������������p���ɍv�������B
|
��W��i1992�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
(�O���[�v)
�}�����ꎁ
����`�� |
���{�d�C(��)
�@���G���N�g���j�N�X������
�@����b�����������ے�
NEC ��b������
�@���� |
�ʓ��o�͌��d�Z���f�q(VSTEP)�̊J����ʂ��Č�����Z�p�ɑ���ȍv���������B
|
| ����@�C�� |
�^�A�� �C�ے��C�ی�����
�@�C�ۉq���E�ϑ�
�@�V�X�e��������
�@��R�������@���� |
�s�i�g�D�{�R���Ό�̐��w���G�[���]���̊ϑ���ʂ��āC�n�����v���ւ̃��C�_�[�̗L�p���𗧏����B
|
��V��i1991�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
| ��Ì��ꎁ |
�����H�Ƒ�w
�@�������H�w������
�@���� |
�����^�����𑜓x���w�������̊J����ʂ��āC�傫�Ȕg�y���ʂ����҂ł���V�Z�p���m�������B
|
| �v�Ԙa���� |
�O�H�d�@(��)
�@����������
�@�ʎq�G���N�g���j�N�X
�@������
�@��1�O���[�v
�@�}�l�[�W���[ |
�O�������W�ω�H�Z�p��p�����������j���[���`�b�v�̊J����ʂ��āC������Z�p�ɑ���ȍv���������B
|
��U��i1990�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
| �O���c�쎁 |
�ʏ��Y�ƏȍH�ƋZ�p�@
�@�d�q�Z�p����������
�@���Z�p��
�@���@�\���������� |
���f�B�X�N�J�[�g���b�W�̋K�i�J���ɂ����Ē��S�I�������ʂ����C���ەW�����ɑ���ȍv���������B
|
(�O���[�v)
���@�@����
�K���G�v��
�ߊԋP���� |
(��)�x�m�ʌ�����
�@��茤����
�@�ʐM�E�F����������
�@���V�X�e��������
�@����
���@���V�X�e��������
�@������@����
���@���V�X�e��������
�@����� |
�ʑ��ϒ��Ɋւ���e��̌��ϕ����Z�p���J�����C�R�q�[�����g���ʐM�Z�p�̎��p���Ɍ����āC����ȍv���������B
|
��T��i1989�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
(�O���[�v)
������
���{�a�j�� |
���{�d�M�d�b(��)
�@��錤���J���Z���^�[
�@�`���V�X�e��������
�@���ʐM�������@�@
���{�d�M�d�b(��)
�@���{�ꌤ���J���Z���^�[
�@�`���V�X�e��������
�@���ʐM������ |
Er�h�[�v�t�@�C�o��������̌��ʐM�V�X�e���ɂ�����D�ꂽ��������ю��p���������C���ʐM�Z�p�J���`���ɐV���ȗ�����N�������B
|
��S��i1988�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
| �����@�_�� |
����w
�@�H�w���d�q�H�w��
�@�����@�@ |
��܊i�q��p�������f�B�X�N�p�s�b�N�A�b�v�Ȃǂ̊J���ɂ��C��IC�Z�p�ɐV�����W�J�������炵���B
|
| �����C���� |
���\�[(��)
�@�V�ޗ�������
�@������ |
�����C���������\�`���f�B�X�N���p���ւ̎w�j�������C���f�B�X�N�Z�p�S�ʂ̐i�W�ɁC����ȍv�����s�����B
|
��R��i1987�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
| �ɉꌒ�ꎁ |
�����H�Ƒ�w
�@�����H�w������
�@�����@ |
�ʔ����f�o�C�X�C�}�C�N�������Y�Ȃǂ̐擱�I�������s���C�����ʂ��ă}�C�N���I�v�e�B�N�X�̐U���ɑ傫�ȍv���������B
|
(�O���[�v)
���쐳�_��
�r���� |
�ʏ��Y�Ə�
�@�H�ƋZ�p�@
�@�d�q�Z�p����������
�@�d�g�d�q��
�@�I�v�g�G���N�g���j�N�X
�@�������@��C������
(��)�쑺����������
�@�Z�p�Y�ƌ�����
�@�@�\�f�o�C�X�f��
�@�Y�ƌ������@���� |
���Y�Ǝs��K�͂̏����\���ɓ���C���S�I�������ʂ����C���Y�Ƃ̏����r�W��������ɑ傫���v�������B
|
��Q��i1986�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
(�O���[�v)
������l��
�㓡�T�ꎁ
�����M�Y�� |
���{�d�C(��)
�@���G���N�g���j�N�X�������@����
���{�d�C(��)
�@C&C������@�����㗝
���{�d�C(��)
�@C&C�V�X�e���������@�ʐM��������C |
���������������ؓI�ɏ��������B
|
��P��i1985�N�x�j
| ��� | ���@�@�� | ��ܗ��R |
|---|
| �_�J���u�� |
������w
�@�H�w�� �d�q�H�w��
�@�������@�@ |
������f�q�̐��\���E���C�����I�C�Z�p�I�ɘ_���C�������x�C����d�͂̓_������C��������Ɏg�����Ƃ̉\�������������B
|
| ���c���玁 | ���{�d�M�d�b(��)
�@NTT�ʐM�ԑ�ꌤ����
�@�`���V�X�e��������
�@���� |
�������Ҍn�̃f�B�W�^�����C�V���O�����[�h�������������B |
OITDA
|